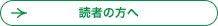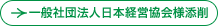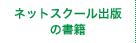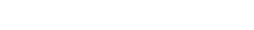全経簿記能力検定
- こんな人におススメ
-
- 企業の経理・会計担当者
- 個人事業主の方
- コスト管理を求められる管理者
- 就職をお考えの学生の方
- 税理士試験への挑戦をお考えの方
- 資格のメリット・活かし方
-
- 就転職に有利になる
- 自社や取引先の財務諸表から長所や短所の分析、経営状態の把握ができる
- 原価管理の基本的な考え方が身に付く
- 税理士試験の受験資格が得られる(上級のみ)
- 受験資格
- 年齢、学歴、国籍など、一切制限はありません。
- 試験日(目安)
-
毎年5月、7月、11月、2月
※上級は7月、2月のみ実施 - 受験料
-
上級:7,800円(税込)
1級商業簿記・財務会計 2,600円(税込)
1級原価計算・管理会計 2,600円(税込)
2級商業簿記:2,200円(税込)
2級工業簿記:2,200円(税込)
3級:2,000円(税込)
基礎簿記会計:1,600円(税込) - 試験科目
-
上級:商業簿記・財務会計・原価計算・管理会計
1級:商業簿記・財務会計、原価計算・管理会計
2級:商業簿記、工業簿記
3級:商業簿記
基礎簿記会計:商業簿記
※1級については、商業簿記・財務会計または原価計算・管理会計の1科目だけ合格し、1年以内に残りの科目に合格した場合、1級合格証書の交付となる。 - 制限時間
-
上級:商業簿記・財務会計90分、原価計算・管理会計90分
1級商業簿記・財務会計:90分
1級原価計算・管理会計:90分
2級商業簿記:90分
2級工業簿記:90分
3級:90分
基礎簿記会計:90分 - 内容
-
-
上級:
商業簿記 / 財務会計(上場企業)
①上場企業のCFO,公認会計士や税理士などの会計専門職およびその候補者として必要な簿記及び財務会計に関する事柄を理解できる。
②大規模株式会社組織を計数の観点から管理するため,ならびに,公認会計士や税理士又はその候補者として業務を行うために,会計情報を作成及び利用できる。
原価計算/管理会計
製造・販売過程に係る原価の理論を理解したうえで,経理担当者ないし公認会計士を含む会計専門職を目指す者として,原価に関わる簿記を行い,損益計算書と貸借対照表が作成できる。また,製造・販売過程の責任者ないし上級管理者として,意思決定ならびに業績評価のための会計を運用できる。
-
1級:
商業簿記・財務会計(大規模株式会社)
①会社法による株式会社のなかで商業を前提にし,主たる営業活動のみならず,財務活動や投資活動など,全般的に管理するために必要な簿記及び財務会計に関する基本的な事柄を理解できる。
②大会社の経理・財務担当者ないし経営管理者として計数の観点から管理するための会計情報を作成及び利用できる。 連結財務諸表については,会計人として初歩的知識を保有する。
原価計算・管理会計 (中小規模企業)
製造業の経理担当者ないし管理者として,原価の意義や概念を理解したうえで,複式簿記に精通し,製造過程の帳簿を作成できるとともに,その内容を理解でき,製造原価報告書および製造業の損益計算書と貸借対照表を作成できる。また,作成した製造原価報告書と損益計算書を管理に利用できる能力を持つ。
-
2級:
商業簿記(中規模株式会社)
①会社法による株式会社を前提とし,小売・卸売業のみならず他業種にも応用できる簿記,とりわけ資本の管理(調達・運用)のために必要とされる簿記の仕組みを理解できる。
②中規模な株式会社の経理・財務担当者ないし経営管理者として計数の観点から管理するための会計情報を作成及び利用できる。
工業簿記(製造業簿記入門) (工業簿記の基礎)
製造業における簿記の学習導入部と位置付け,現場の経理担当者として,工程管理のための実際原価に基づく基本的な帳簿を作成でき,また,これらを管理する能力を持つ。
-
3級:
商業簿記(小規模株式会社)
①小売業や卸売業(商業)における管理のために必要とされる簿記の基本的な仕組みを理解できる。
②小規模な株式会社の経理担当者ないし経営管理者として計数の観点から管理するための会計情報を作成及び利用できる。
-
基礎簿記会計:
基礎簿記会計(簿記会計学の基本的素養が必要な営利・非営利組織)
①組織が営利か非営利かに関係なく必要とされる簿記の仕組み及び会計学の基本的な考え方を理解できる。
②個人事業主及び極めて小規模な株式会社の経営者や経理担当者,あるいはマンション管理組合の役員として関連組織を計数の観点から管理するための会計情報を作成及び利用できる。
-
上級:
商業簿記 / 財務会計(上場企業)
- 合格基準
-
- 各級とも1科目100点満点とし、全科目得点70点以上を合格とする。ただし、上級は、各科目の得点が40点以上で全4科目の合計得点が280点以上を合格とする。
- 合格率の目安
-
上級:おおむね15%程度
1級商業簿記・財務会計:おおむね20~50%程度
1級原価計算・管理会計:おおむね50~70%程度
2級商業簿記:おおむね50~70%程度
2級工業簿記:おおむね60~80%程度
3級:おおむね50~70%程度
基礎簿記会計:おおむね70~90%程度 - その他備考
-
※詳細は主催者である全国経理教育協会の簿記能力検定試験ホームページ【http://www.zenkei.or.jp/exam/bookkeeping】をご覧ください。
全経簿記の学習法
■ 書籍で学習
■ モバイルスクールで学習(1~3級・基礎簿記会計)
■ WEB講座で学習(上級)
書籍で学習
自分のペースで学習したいという方には、書籍での学習がおススメです。ネットスクールでは、1~3級及び基礎簿記会計に関しては、「公式テキスト」並びに「公式問題集」を刊行しています。
また、上級対策については、多くの方にご愛用頂いている過去問題集などを刊行しています。
→ネットスクールの全経簿記対策書籍をWEB-SHOPで探す
モバイルスクールで学習(1~3級・基礎簿記会計)
1~3級及び基礎簿記会計については、「モバイルスクール」にて解説動画を配信中です。
気軽に受講して頂くことが可能です。
→モバイルスクールの全経簿記対策動画
WEB講座で学習(上級)
ネットスクールでは、全経簿記上級対策のWEB講座を開講中です。
→ネットスクールの全経簿記上級対策WEB講座